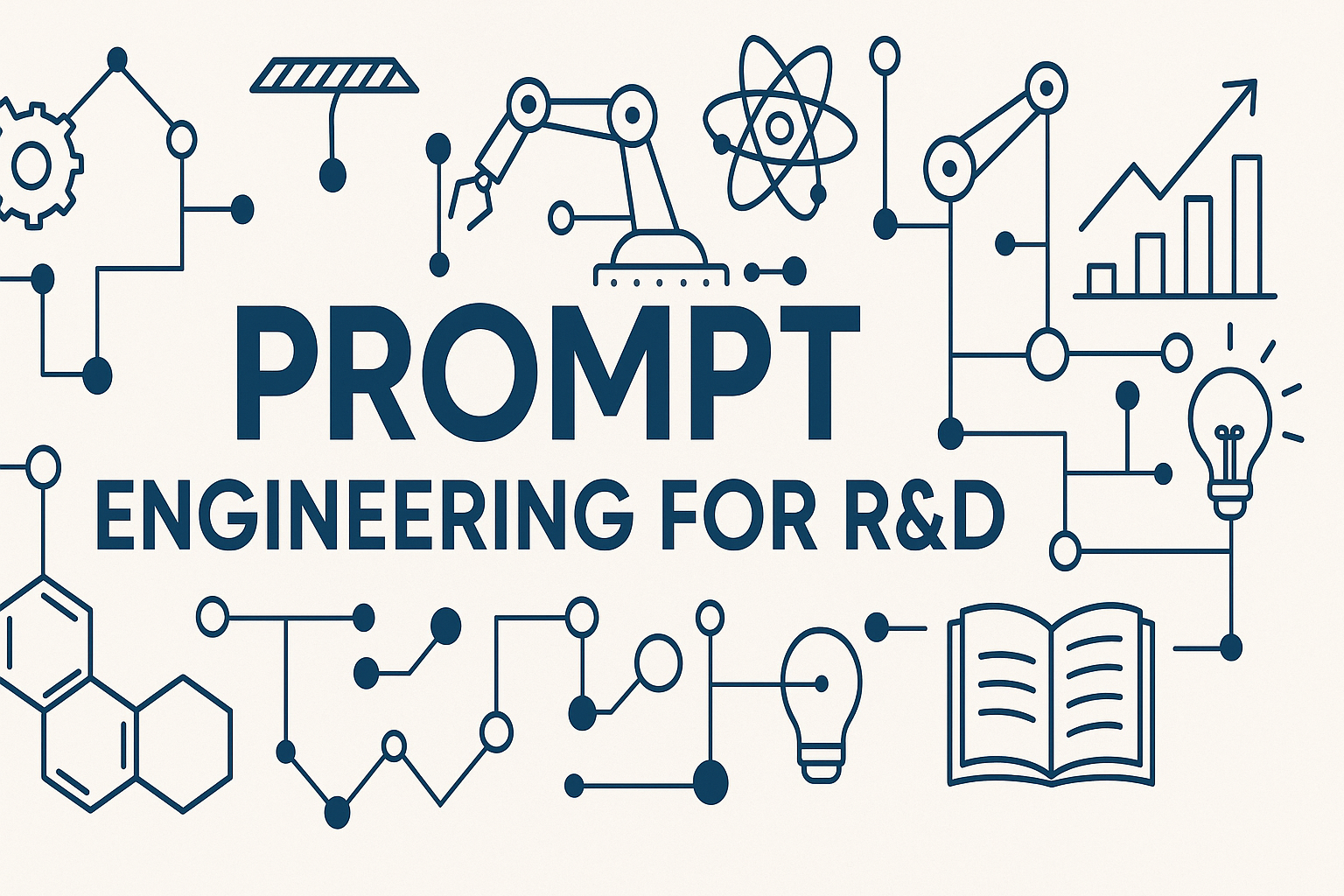生成AI(Generative AI)は、市場・技術の調査や分析、プロジェクト計画の立案、ドキュメントの作成など、R&D現場において従来時間と労力を要した業務を大幅に効率化することが可能です。また、技術者・研究者の思考の幅を広げ、新たな価値と技術の想像・構想を強力に支援する可能性を秘めています。
しかし、モノづくり専門情報メディア「MONOist」が実施したアンケート調査によれば、80%以上の技術者が生成AIを「役立つ」と回答したにもかかわらず、「日常的に使っている」と回答した人は2割に留まっているという結果が出ています。1) この「期待と現実のギャップ」は、生成AIの活用が思ったほど進んでいない現状を如実に示しています。
この要因としては、R&D業務の持つ特性(不定形かつ曖昧性が高く、様々な状況に合わせてプロセスを修正する必要があること、思考業務の割合が高く、その中身が見えにくいことなど)や、生成AIを使うことに対する現場の技術者・研究者の心理的な抵抗感や懸念など、様々考えられますが、その中の一つに、「プロンプト(指示文)の書き方が分からない」「欲しい情報がうまく引き出せない」といったプロンプティングスキルの不足があると考えられます。生成AIは、入力されたプロンプトによって応答の質が大きく変わります。R&Dのように高度な知識が求められる分野では、構造的かつ明確なプロンプト設計が不可欠です。しかし、多忙な実務を抱える中で、現場のすべての技術者・研究者がこのスキルを独学で身につけるのは極めて困難です。また、生成AIを利用するたびにプロンプトを作成していることは、実用上現実的ではありません。
そこで鍵になるのが「標準プロンプト」の整備と共有です。これは、状況に合わせて柔軟に対応しながら、誰でも一定の品質でAIを活用できるようにする仕組みであり、組織全体での生成AIの活用を後押しします。
標準プロンプトは次の2つの要素から構成されます。
- ベースプロンプト:七里式や深津式など、普遍的なプロンプト設計手法に基づいて作成された骨組み部分。文体や指示方法などの共通仕様を担う。
- アプリプロンプト:用途に応じた業務知識を追加した実用的な部分。例えば、「市場調査」「特許分析」「アイデア出し」など、特定の業務に特化した指示が含まれる。
この2層構造により、ベースは共通化しつつ、業務に応じて柔軟なカスタマイズが可能になります。さらに、アプリプロンプト部分は業務内容の変化に応じて更新できるため、継続的な改善も行いやすいのが特徴です。
標準プロンプトを設計する上で、肝になるのはアプリプロンプトです。アプリプロンプトを設計するためには、活用対象とする業務の目的を明確にした上で、その思考プロセスおよびフレームワークを具体化し、プロンプトとして落とし込む必要があります。そこには、市場や顧客、技術、そして組織など事業に関する深い知識と理解が不可欠であり、単なる言語的な操作だけでは有効なプロンプトを設計することは不可能です。そのため、アプリプロンプトの設計の中核を担うのは、経験に裏打ちされた豊富な業務知識を持つベテラン人材であり、生成AI活用の成否は彼らをいかに巻き込むかにかかっていると言っても過言ではありません。
標準プロンプトの整備と並行して必要になるのは、現場での導入・教育体制の構築です。現場の技術者・研究者が標準プロンプトを用いた生成AI活用方法を学び、その実践をサポートする仕組みを整備していきます。このような仕組みが整うことで、現場において生成AIを使いこなす共通言語と組織文化が形成されていきます。
生成AIは単なる業務効率化ツールではなく、R&Dの知的生産性の革新をもたらす存在です。そのI活用を本格化させるためには、業務知識を組み込んだ構造的なプロンプトエンジニアリング・スキルを向上させることが鍵となります。「標準プロンプトの構築」と「実践教育の体系化と仕組み化」を進めることで、生成AIは現場の持つ知識と融合し、効果的な活用につながります。
ケミストリーキューブ
平木 肇
1)製造業における生成AIの業務活用動向調査【2025年版】、MONOist編集部
本ウエブサイトに記載されている製品・サービス情報、技術情報、並びにこれらを表現するための文章・図表・画像それらの集合(以下、コンテンツ)に関する著作権は、すべて株式会社ケミストリーキューブ及び著作者に帰属するものです。著作権保有者の許可なく、コンテンツの複製・転載・配布を行うことはご遠慮ください。